放射線治療Q&A
- 放射線治療とはどのような治療ですか。
-Q1手術や薬物療法とは何が違うのですか。
- A
-
放射線治療は、手術と同様にがんのある部分だけを治療する局所治療です。一方、薬物療法は全身に効果を発揮する全身療法です。放射線治療では臓器を取らずに治すことが可能で、からだへの負担が手術より少ないことがほとんどです。局所治療なので効果も悪影響も原則として治療した部分に限られます。
(本書は「正しい情報」をみなさんにお伝えするものです。「副作用」とは薬物療法に使う言葉ですので、文中では聞き慣れた「副作用」ではなく、あえて「悪影響」という言葉を使います。)
-Q2放射線診断と放射線治療は何が違うのですか。
- A
-
どちらも放射線を用いることは同じですが、放射線診断は、放射線を使って患者さんの体内情報を画像化し、病気の「診断」を行うことを目的とします。放射線をからだの調べたい部分に照射して、通り抜けて出てきたわずかな放射線を検出することで、臓器や病気の状態を調べます。一方、放射線治療は、患者さんのからだの中にあるがんなどの病気めがけて強い放射線を照射して、がんの「治療」を行うことを目的とし、放射線により病気の細胞を死滅させます。
-Q3放射線治療はどこで受けることができ、誰が行うのですか。
- A
-
放射線治療はリニアック(直線加速器)などの放射線治療装置をもっている病院で受けることができます。日本中の多くの病院に「放射線科(放射線部)」という診療科(部門)がありますが、その多くが「放射線診断」(Q2参照)のみを行っている施設で、「放射線治療」を行っている施設は約800施設です。放射線治療は多くの職種から構成される「チーム医療」です。医師(放射線腫瘍医)、診療放射線技師、看護師だけでなく、医学物理士、放射線治療品質管理士など、他の部門にはいない放射線治療に関わる専門職種が携わっています。
-Q4転移したがんにも放射線治療は有効ですか。
- A
-
転移したがんに対しても放射線治療は有効です。がんが局所にとどまっている場合には治す目的で、全身的に転移している場合では症状を和らげる目的などで放射線治療が行われます。頻度の高い脳、肺、肝、骨への転移に対する放射線治療はそれぞれの項目(Q14、Q16、Q17、Q19)をご覧ください。
- 放射線治療を受けるにあたっての心配ごとについて教えてください。
-Q5放射線治療はからだに悪くないですか。
放射線による悪影響(副作用)について教えてください。
- A
-
放射線治療によるからだの正常な部分への悪影響は、治療中から終了後数か月までの影響と、数か月以降に起こる影響に分けられます。いずれも照射した部分が原因で起こる変化です。症状や程度は照射部位とその範囲、放射線の量や種類によって異なり、抗がん剤の併用や年齢、全身状態も影響します。
家族や周囲の人に影響はありませんか。
- A
-
放射線治療のほとんどを占める外部照射では、放射線は照射の時、瞬時にからだを通り抜けます。放射線そのものがからだに残ることはないので、家族や周囲の人への影響はありません。小線源治療の線源が体内に残っている場合、内用療法(標的アイソトープ治療)ではからだから放射線が出ますので、注意を守って周囲への影響を避けましょう。
妊娠や出産に影響はありませんか。
- A
-
男女とも、照射部位が下腹部(卵巣や精巣)から離れていれば、生殖にほとんど影響は及びませんが、影響がまったくないわけではありません。とくに妊娠可能年齢の女性は注意が必要ですので、不安な方は担当の放射線腫瘍医に尋ねてください。
-Q6放射線治療の費用はどれくらいかかりますか。粒子線治療の費用や高額療養費制度、先進医療などについても教えてください。
- A
-
放射線治療の費用は使う放射線の種類や治療方法、全体の治療回数で決まります。外部照射でかかる費用は、治療のための準備と日々の治療に関わるものに大別されます。複雑な治療技術を使うため、回数が多くなるほど費用は高くなります。また、健康保険の負担割合で支払う費用が変わります。
-Q7放射線治療はどれくらいの日数がかかりますか。
- A
-
1回(1日)で終わるものから1か月以上かかるものまであります。放射線腫瘍医の診察によって最適な治療回数が決まります。
-Q8放射線治療中も普通に生活できますか。
- A
-
ほとんどの患者さんは、放射線治療をはじめる前と同様の生活を送ることができます。ただし、放射線治療の範囲や方法、ほかの治療方法との組み合わせにより、体調が変化する患者さんもいます。こうした変化が出たら、放射線腫瘍医による安静や投薬の指示に従ってください。くわしくはQ11を参照してください。
- 放射線治療を受けることにしましたがもう少し教えてください。
-Q9放射線治療の実際の手順について教えてください。
- A
-
放射線治療における実際の手順を以下の項目ごとに説明します。
病理組織診断・放射線診断
↓
病期(ステージ)決定
↓
放射線腫瘍科を受診、診察、説明と同意
↓
固定具作成・治療計画CT撮影
↓
照射部位決定・コンピュータによる治療計画・線量分布を評価して決定
↓
毎日の放射線治療開始、定期的な診察
放射線治療をするかどうかはどのように決めるのですか。
- A
-
最初から「首にしこりができたから、ここに放射線を当ててほしい」と言って放射線腫瘍科を受診する患者さんはまずいないと思います。放射線腫瘍科は患者さん自らが最初に受診する診療科ではなく、基本的には他の診療科で病気の診断がなされ、その治療法の選択肢の1つとして紹介され、受診することがほとんどです。
放射線治療計画とは何ですか。
- A
-
放射線を照射する範囲の設定や照射する線量を計算することを「放射線治療計画」といいます。
どのように放射線治療が進むのか教えてください。
- A
-
放射線腫瘍科を受診し治療方針が決定した後で、最初に行われるのは「治療計画CT」の撮影です。病院によって異なりますが、早ければ診察の後に引き続き行われます。その後、Q9-2で説明した「放射線治療計画」が行われます。治療計画が完成した後に照射開始となり、早ければ診察日の翌日、複雑で特殊な治療では1~2週間後となる場合もあります。
照射法の変更をすることがあるのはなぜですか。
- A
-
照射法の変更は、腫瘍に線量を集中するため、正常の部分への悪影響を避けるためなどのいくつかの目的のために行われます。
放射線治療は外来通院と入院のどちらがよいのでしょうか。
- A
-
これまでの長い放射線治療の積み重ねから、「週5回の照射でうまく治療できる」ように、1回の照射線量が考慮されています。その全治療期間の中では、数日程度の祝日による休止が入っても治療効果には大きな差がないと考えられています(Q7参照)。
放射線治療は外来通院と入院のどちらがよいのでしょうか。
- A
-
通常、多くの放射線治療は外来通院での治療が可能です。
土日、祝日の照射を休みにすると、治療の効果は弱くなりますか。
- A
-
これまでの長い放射線治療の積み重ねから、「週5回の照射でうまく治療できる」ように、1回の照射線量が考慮されています。その全治療期間の中では、数日程度の祝日による休止が入っても治療効果には大きな差がないと考えられています(Q7参照)
自分の都合で治療を休んでも、効果に影響はないですか?
- A
-
全治療期間を通して数日程度の休みであれば、治療効果にほとんど影響はないと思われます(Q7参照)。
患者によって治療の回数が違うのはなぜですか。
- A
-
がんを完治させる、術後の再発予防、症状緩和(痛みを取るなど)など、放射線治療の目的によって必要な放射線の総線量は変わるからです。また、がんの種類や進行度によっても回数が異なります。
放射線治療を一度受けたら、繰り返し受けられないのですか。
- A
-
正常組織が放射線によるダメージを受けた場合、いったん回復はするものの、潜在的にはダメージが残存し、何年経っても完全には回復しないと考えられています。また、多くのがんの治療では、正常組織が許容できる限度近くまで照射していることが多いため、原則として、同じ部位に再度、同じ線量を照射できないことがほとんどです。
-Q10放射線療法の併用療法について教えてください。
薬物療法との併用はどのような場合に有効ですか。
- A
-
がんが大きく放射線治療のみでは治りきるのが難しい場合や、転移を予防する効果を考えると、薬物療法と放射線療法を有効に併用すれば強力な治療手段となりえます。
手術との併用はどのような場合に有効ですか。
- A
-
がんが大きい場合、正常の機能をできるだけ損ないたくない場合、術後の残存腫瘍を根絶する目的などでは、手術と併用することで、がんが治る率が高くなります。
その他の治療方法との併用は有効か教えてください
- A
-
温熱療法、免疫療法などとの併用は細胞レベルでは有効性が示されていますが、臨床的には十分な成果が得られていません。
- 放射線治療中から直後の生活について教えてください。
-Q11放射線治療中から直後の生活上の注意について教えてください。
食事で気をつける点はありますか。
- A
-
治療の内容によっては食事の注意が必要です。とくに、口腔や咽頭、消化管などに放射線が当たる場合は食事に気をつける必要があります。刺激物や消化の悪いものなどを避けて、栄養と水分を効率よくとることが大事です。また、食事の形態、栄養バランス等にも工夫が必要です。
入浴、温泉、サウナ、岩盤浴は大丈夫でしょうか。
- A
-
温泉・サウナ・岩盤浴に関しては照射期間中と治療終了直後は避けたほうがよいでしょう。また、海水浴やプールも同様です。
仕事や家事は今までどおり可能ですか。
- A
-
外来通院の場合、基本的に照射期間中の通院・治療に要する時間的制約以外の制約はほとんどありません。肉体的・精神的に過度の負担とならない程度であれば、今までどおり仕事や家事を行ってもかまいません。
旅行やスポーツはどの程度できますか。
- A
-
旅行やスポーツも、肉体的・精神的に過度の負担がかからない程度でしたらかまいません。
飲み薬や塗り薬は今までどおり使ってよいですか。
- A
-
一般的な薬はほとんど問題ありませんが、薬の種類や放射線治療の内容により異なるので、一概に断定できません。放射線腫瘍医に現在使用している薬を提示して相談してください。とくに抗がん剤、ホルモン剤、免疫抑制剤や塗り薬等では注意が必要です。
インフルエンザなどの予防接種を受けてよいですか。
- A
-
一般的には問題ありませんが、必ず事前に担当の放射線腫瘍医に相談してください。
タバコを吸ったりお酒を飲んだりしてもよいですか。
- A
-
タバコを吸うと放射線治療の悪影響が増強されますので、禁煙を強くおすすめします。状況によりますが、お酒を飲んでもよいと担当の放射線腫瘍医が判断した場合も適量を守りましょう。
むだ毛の処理は今までどおり行ってよいですか。
- A
-
照射範囲内でなければかまいませんが、放射線治療の範囲やその近くのむだ毛の処理はなるべく避けてください。どうしても脱毛が必要な患者さんは、照射部位の皮膚を傷つけないように行ってください。
あんま、マッサージ、針、灸、エステなどは大丈夫ですか。
- A
-
照射部位に影響がない限りは大丈夫ですが、判断しにくければ照射期間中は避けたほうが賢明です。乳がん術後のマッサージ・リハビリ等は放射線腫瘍医の指示に従ってください。
-Q12放射線治療中に不安になりがちな点について教えてください。
治療の悪影響がない時は、治療効果もないのでしょうか。
- A
-
がん細胞と正常な細胞とでは、同じ量の放射線を当ててもその影響の度合いが異なります。ですから、治療の効果(がん細胞が受ける放射線の影響)と悪影響(正常細胞が受ける放射線の影響)の程度は必ずしも比例するものではありません。治療が進んでも悪影響があまりないからといって、「治療が効いていないかもしれない」と心配する必要はありません。
さらに、最近ではCT・MRI・PETなどの画像診断技術の進歩や、コンピュータ技術の発展により、放射線を当てたい箇所(がん)に集中させ、当てたくない箇所(がん周囲の正常細胞)になるべく当てないように治療できるようになってきました。これにより、治療効果を落とすことなく、治療の悪影響を減らせることが期待されています。
また、同じ部位のがんであっても、放射線の当たる範囲や当たり方は患者さんごとに異なり、それによって治療の悪影響の程度も変わりますので、ほかの患者さんと比較する必要もありません。
悪影響がいつ出るか心配なのですが。
- A
-
放射線治療の悪影響には、治療中から終了後まもなく現れる急性期の悪影響と、治療が終わって数か月以降に出る晩期の悪影響があります。
治療箇所と違う場所に印が付いているのですが。
- A
-
治療計画用のCT画像を撮影する際、皮膚や固定具の表面に印を書きますが、これは治療装置の照射口を治療箇所に正確に合わせるための印です。心配する必要はありません。
治療用の印が消えそうなのですが。
- A
-
位置を合わせるための印(マーク)は、消えにくいインクを使用したり、テープを貼ったりするなど各病院でさまざまな工夫をしていますので、衣類ですれたり、からだを拭いたりする程度では落ちません。Q11-2で説明したように、短い時間ならば入浴も可能です。
治療中に咳やくしゃみが出そうになったらどうすればよいですか。
- A
-
照射時、スタッフは治療室から出ており、操作室で治療室内の様子をモニタで見ています。咳が出そうな時は手を挙げるなどして合図してください。また、照射するタイミングを放送で知らせることもできますので、咳が心配な時はスタッフに相談してください。
-Q13放射線治療の効果はどのように判定するのか教えてください。
- A
-
放射線治療の効果を見る時期(タイミング)や方法は、治療の目的や病状によりさまざまですが、放射線治療の効果が出てくるまでにはある程度の時間がかかります。通常は放射線治療の終了後1~2か月ほど経過してから効果判定を行いますが、いつ頃・どのような検査を行うかは、担当医とよく相談してください。
放射線治療の効果はいつわかるのですか。
- A
-
放射線でがん細胞の遺伝子に傷ができると、がん細胞は遺伝子に傷を抱えたまま無理に分裂しようとして死滅します(Q24-1)。細胞が分裂するまで傷の影響が出ないため、放射線治療の効果が出てくるまでにはある程度の時間が必要です。
放射線治療の効果はどのような方法でわかるのですか。
- A
-
治療効果を見る方法として、主に画像検査(内視鏡や超音波なども含む)、診察所見、血液検査、自覚症状の改善が挙げられます。
- 放射線治療部位別の治療法を教えてください。
-Q14脳・脊髄への放射線治療について教えてください。
脳に放射線を当てて大丈夫なのでしょうか。治療の悪影響と対処法について教えてください。
- A
-
脳はからだの働きを調節する大切な臓器です。放射線治療は脳の病気を治すことや、進行を抑えるうえで有用な治療です。以下に述べるような症状を伴うこともありますが、これらは生活の工夫や薬剤の使用で抑えることが可能です。症状に注意しつつ、最大限の効果が出るように治療を行います。
脳腫瘍のタイプによって放射線治療法が違いますか。
- A
-
放射線治療には、すべての脳を含むように照射する全脳照射、腫瘍およびその周囲を中心に照射する局所照射、脳内にある脳室を照射する全脳室照射などさまざまな方法があります。脳にはさまざまなタイプの腫瘍が発生するため、腫瘍のタイプ、局在、大きさ、広がりなどを評価し、手術、薬物療法など他の治療法との併用も考慮したうえで、病態に即した治療を行います。
全脳照射、全中枢神経系照射とはどのような治療ですか。
- A
-
全脳照射は脳全体を照射の対象とする照射方法で、全中枢神経照射はこれに脊髄全体も加えて照射する方法です。
定位照射はどのような時に有用ですか。
- A
-
定位照射は脳転移、聴神経腫瘍、下垂体腫瘍、髄膜腫、脳動静脈奇形(AVM)などの小さく、境界が明瞭な病変に対して疾患に対してよく行われます。
脳転移に対する放射線治療について教えてください。
- A
-
症状のある脳転移では手術や放射線治療が有用です。患者さんの全身状態、その後の病状の見通し、脳転移の大きさや数などを検討し、放射線療法であれば定位照射もしくは全脳照射を行います。限局した小細胞肺がんなどで、治療により良好な効果が得られた場合には、画像上で脳転移がなくても、予防的に全脳照射を行うことがあります。
脳腫瘍に粒子線治療は有用ですか。
- A
-
水素の原子核を用いた陽子線治療、炭素の原子核を用いた炭素イオン線治療は「粒子線治療」と総称されていますが、通常の脳腫瘍では粒子線治療の利点ははっきりしません。また、まだ研究段階ですが、アルファ線を照射するホウ素中性子捕獲療法は今後の発展が期待されています。
散髪、洗髪、白髪染め、パーマをしても大丈夫でしょうか。脱毛はいつ頃治りますか。
- A
-
頭皮に放射線が当たる場合、皮膚炎を起こして、過敏で傷つきやすい状態になります。清潔を保ち、散髪、通常のシャンプー・リンスを使った洗髪、髪染め、パーマは控えてください。脱毛は一時的なもので、放射線治療終了の数か月後には次第に髪が生え始め、半年~1年でほぼ元通りの状態に戻ることが一般的です。
良性の病気ではどのような時に有用ですか。
- A
-
髄膜腫、下垂体腺腫、聴神経鞘腫などの良性脳腫瘍のほかに、脳動静脈奇形(AVM)や硬膜動静脈奇形などの脳血管の奇形で、放射線治療が行われることがあります。
脊髄腫瘍への放射線療法はどのような時に有用ですか。
- A
-
脊髄の中にできる神経膠腫では、まず手術による摘出を行い、その後に放射線治療を検討します。悪性腫瘍が硬膜外に転移し、硬膜外より脊髄が圧迫され、痛み、運動麻痺、感覚障害などの症状が明らかな場合には、症状緩和のため、速やかな放射線治療が必要です。
脊髄圧迫に対する放射線療法はどのような時に有用ですか。
- A
-
がんが脊椎へ骨転移して脊髄が圧迫されてくると、胸椎や腰椎では下肢の麻痺や膀胱直腸障害が、頸椎では上肢も含めた四肢麻痺や膀胱直腸障害が起こります。至急、手術(椎弓切除術)や放射線治療により、圧迫を除去することが必要です。放射線治療の緊急照射をします。
-Q15頭頸部(顔からのど)への放射線治療について教えてください。
手術より放射線治療のよい点は何ですか。
- A
-
放射線治療では、手術のようにがんがある部分を取るのではなく、がん細胞を放射線で殺して治療しますので、がんがあった場所の正常部分を残して治療できます。そのため、治療の負担が少なく、治療後の生活の質が手術より保たれるなどの利点があります。
喉頭がんは声への影響はありませんか。
- A
-
放射線治療では手術のようにがんがある部分を取って治すわけではありませんので、声帯は元のまま残ります。患者さんによっては声が多少太くなることがありますが、影響はほとんどないといえます。治療直後は炎症で声がかれることがありますが、のどを安静にしていれば、数か月以内に元通りの声に戻ることがほとんどです。
治療法を選ぶ時のポイントはどのような点ですか。
- A
-
まずは機能や形態の保持を考えながら、手術主体か放射線治療主体かを選択します。放射線治療を選択した場合、通常の外部放射線治療に加えて、強度変調放射線治療、小線源治療、粒子線治療などをおすすめすることがあります。進行例では、放射線治療に抗がん剤や分子標的薬などの薬物療法の併用をおすすめすることがほとんどです。
口やのどの治療による悪影響と対処法について教えてください。いつ頃治りますか。
- A
-
口やのどの治療による悪影響で主なものは粘膜炎、味覚障害、唾液腺障害とそれによって起こる口内乾燥、皮膚炎です。治療を始めて2~3週間から症状が出始まり、治療を終えて1か月くらいで症状が落ち着くことが多いのですが、口腔乾燥は長引きます。口やのどの安静に加えて、うがい薬、吸入薬、飲み薬、塗り薬などで対処します。
治療中のひげ剃りや化粧品の使用は問題ありませんか。
- A
-
ひげ剃りは電気シェーバー等の刺激の少ないもので軽く行い、カミソリの使用は皮膚の荒れがひどくなることがあるのでやめましょう。放射線が当たっている部分への化粧品の使用は、原則的には避けてください。
歯みがきや歯科治療は問題ありませんか。
- A
-
口の中に放射線が当たる治療を受けている患者さんは、歯ぐきや口の中の粘膜が弱っていますので、普通に歯みがきをするのは避けましょう。歯ブラシを使う時は歯だけ磨いて、歯と歯ぐきの間や舌は専用のスポンジやブラシ、綿棒などで清掃しましょう。放射線が当たった部分の抜歯は、照射後年数が経っても下顎骨の壊死などの原因となるので、必ず担当の放射線腫瘍医に相談してからにしてください。
甲状腺がんへの放射線療法について教えてください。
- A
-
甲状腺がんの放射線療法は、放射性ヨードを飲む治療法(放射性ヨード内用療法)が一般的です。放射線をからだの外から当てる外照射法は、手術や放射性ヨード内用療法が適応とならない場合や、これらの治療後の追加治療として行われています。
眼の腫瘍ですが視力への影響はありませんか。
- A
-
眼の腫瘍の種類と大きさや、どの部分に放射線が当たるかによって放射線治療が視力に影響する程度は変わります。視神経に強い放射線が当たる場合には、視力への影響が大きくなります。しかし、眼球摘出手術による失明に比べると視力が温存できますので、影響は少ないといえます。眼の悪性黒色腫や涙るい腺せん腫瘍では粒子線治療が有用です。
-Q16胸部(乳房、肺、食道など)への放射線治療について教えてください。
肺がんの治療法を選ぶ時のポイントはどのような点ですか。
- A
-
肺がんの治療法を選ぶにあたって大事なポイントは、1.がん細胞の種類や特徴、2.がんの進行度、3.患者さんの体調(合併症など)と考え方の3つです。
肺気腫や間質性肺炎があっても治療できますか。
- A
-
肺気腫や間質性肺炎があると放射線治療ができないことはありませんが、肺気腫や間質性肺炎の状態等によっては悪影響のリスクが高いため治療をおすすめできない場合もあります。
肺腫瘍に対する定位放射線治療とはどのような治療ですか。
- A
-
定位放射線治療は一般向けの報道で“ピンポイント照射” の名前で紹介されている治療で、原発性肺がん、転移性肺がんを問わず5cmまでの比較的小さい病変が対象となります。定位放射線治療の特徴は、1.高精度の位置合わせ、2.病変へのビーム集中、3.1回高線量で短期間治療の3つです。
肺腫瘍に対する粒子線治療はどのような時に有利ですか。
- A
-
肺腫瘍に対する治療で粒子線治療が有利なのは、1.間質性肺炎や肺気腫などの合併症をもった患者さんの治療、2.エックス線が効きにくいタイプの腫瘍に対する治療の場合です。
肺がんで放射線治療に薬物療法を加える必要はありますか。
- A
-
1.小細胞肺がんの治療、2.局所進行期(腫瘍が大きく周囲に浸潤していたリンパ節転移があっても他の臓器への転移がない状態)の非小細胞肺がんの治療では、放射線治療に抗がん剤治療を加えることで放射線治療だけの場合と比べて治療効果がよくなる(生存期間が延びる)ことがわかっています。放射線治療と抗がん剤(薬物療法)を合わせて行う治療を化学放射線療法といいます。
肺腫瘍に対する放射線治療の悪影響と対処法について教えてください。
- A
-
肺腫瘍に対する放射線治療の悪影響は、1.放射線肺炎、2.放射線食道炎、3.骨髄抑制、4.胸水と心嚢水貯留、5.放射線皮膚炎、6.放射線宿酔などです。
乳がん術後の放射線治療は必要なのでしょうか。
- A
-
早期乳がんに対し乳房を温存する手術を受けた場合、乳房を切除した患者さんで4個以上のリンパ節転移があった場合には、放射線治療を行うことで明らかに生存率が向上することがわかっており、術後の放射線治療を強くおすすめします。
乳がん術後の放射線治療の悪影響と対処法について教えてください。
- A
-
放射線治療部位の皮脂腺、汗腺の働きが落ちて皮膚がかさかさしたり、ほてったりすることがあります。治療の後半に軽い日焼けのような放射線皮膚炎が起こりますが、保湿剤や軟膏で対処すれば1か月くらいで収まります。そのほか、まれですが肺炎などが数か月後に起こることもあります。
乳がんを手術せずに放射線治療で治せますか。
- A
-
臨床試験などで、乳がんを手術せずに放射線治療で治すような試みはありますが、現状では手術と組み合わせて治療することが、効果と悪影響の観点から最良です。治りが悪かったり悪影響が強くなったりする場合もありますので、よく考えて慎重に選択してください。
放射線治療後に乳房再建はできますか。乳房再建後には放射線治療はできないのですか。
- A
-
放射線治療後に乳房再建、乳房再建後に放射線治療、どちらの順番でも可能です。ただし、放射線治療は皮膚の機能を落とし傷の治りを悪くしますので、放射線治療後の再建では感染、壊死などの起こる可能性が少し高くなります。
食道がんの治療法を選ぶ時のポイントはどのような点ですか。
- A
-
最も重要なポイントは病気の進行度(病期)です。食道がんの治療は、大きく分けて手術と放射線治療とがあり、病期によって薬物療法を組み合わせることが一般的です。早期の場合は、手術のなかでも内視鏡による切除のみで治療可能な場合もあります。頸部食道がんでは、発声や飲み込みの機能を重視して、放射線治療を選択することもあります。
食道がんへの放射線治療の悪影響と対処法について教えてください。
- A
-
咽頭、消化管の粘膜炎、骨髄抑制、放射線肺炎、皮膚炎、心膜炎・心筋炎、消化管穿孔などの可能性があります。食道に対する放射線治療では、照射範囲が肺がんの場合と同様です。
-Q17上腹部(膵、肝など)への放射線治療について教えてください。
膵がんの治療法を選ぶ時のポイントはどのような点ですか。
- A
-
診断時に手術が可能な場合には手術と術後化学療法が完治を目指した治療として行われます。また、他臓器転移がある場合には化学療法の単独療法が一般的です。一方、他臓器転移はないものの、腫瘍が膵臓の周りの主要血管を巻き込んでいるために手術で取り除くことができない場合(局所進行)には、腫瘍の治療を目的とした薬物療法を同時に併用する化学放射線療法か、単独での薬物療法が選択肢として標準的に行われます。
肝臓がんへの放射線療法はどのような時に行いますか。
- A
-
手術が困難と判断され、局所(範囲が狭い)の病変の場合の局所治療の1つとして、放射線療法があります。放射線療法は、経皮的な局所療法や局所療法が実施できない場合、あるいはこれら局所療法の効果が乏しいと判断される場合、局所療法との併用で効果が高まると判断される場合に行われます。最近では、体幹部定位放射線療法や粒子線治療を用いることで高線量照射が可能となり、治療効果が良くなっています。
肝腫瘍への定位照射や粒子線治療はどのような時に有利ですか。
- A
-
肝臓への体幹部定位放射線治療は、5cm以下の原発巣肝がんや転移性肝がんを治すことを目的として行います。一方、5cmを超える大きな腫瘍や肝臓の血管である門脈や下大静脈に腫瘍が進展している場合でも、先進医療としての粒子線治療で治すことを目的に治療できます。
胆道がんへの放射線治療はどのような時に行いますか。
- A
-
他臓器転移がなく、原発巣やリンパ節転移などの局所のみが進行して手術ができない局所進行の場合には、選択肢の1つに化学放射線療法があります。黄疸などの症状が強い場合には、症状緩和目的として放射線療法が検討されます。また、手術後に切除断端が陽性の場合やリンパ節転移を認める場合には、手術後の化学放射線療法が選択肢の1つとなります。
腎臓がんではどのような時に有利ですか。
- A
-
腎臓がんに対する最も有効な治療法は手術療法です。腎臓の原発巣に対して根治療法として放射線療法を行うことはほとんどありませんが、近年、高齢や合併症などの問題で手術ができない場合に、治療中に針を刺さずに腎臓の腫瘍を治す方法として、体幹部定位放射線治療や粒子線治療が試みられています。原発巣以外では、骨転移、脳転移などの他臓器転移に対する放射線療法は症状緩和に有効です。
胃がんや大腸がんではどのような時に放射線治療を行いますか。
- A
-
原発巣の切除ができない場合や合併症、全身状態の問題で手術ができない場合に、胃や大腸の原発巣からの出血や腫瘍による疼痛や通過障害などの症状緩和目的として、放射線療法が行われます。近年、他臓器転移がなく、原発巣やリンパ節転移などの局所のみが進行している局所進行胃がんに対して、治療成績の向上を目指した化学放射線療法が試みられています。原発巣以外では、骨転移、脳転移などの他臓器転移に対する放射線療法は症状緩和に有効です。
-Q18下腹部(前立腺、子宮、膀胱、直腸など)への放射線治療について教えてください。
前立腺がんの治療法を選ぶ時のポイントはどのような点ですか。
- A
-
前立腺がんに対して行われる放射線治療には、いくつかの種類があります。大きく分けると、からだの中から放射線を当てる小線源治療と、外から放射線を当てる外部放射線治療です。(Q26-1参照)
前立腺がんに対する放射線治療の悪影響と対処法について教えてください。
- A
-
前立腺の上方には膀胱、後方には直腸があり、前立腺の中は尿道が通っています。前立腺がんの放射線治療では、これらの正常臓器に放射線が当たってしまうため、悪影響が出ることがあります。
子宮頸がんの治療法を選ぶ時のポイントはどのような点ですか。
- A
-
比較的早期の子宮頸がん(I~II期)では手術と放射線治療の治療成績に差はなく、いずれも根治的治療が可能です。一方、進行した場合(III~IVA期)は放射線療法が選択されますが、化学療法と同時に行われることがあります。
子宮頸がんでは腔内照射は必要なのでしょうか。
- A
-
腔内照射は単独あるいは外部照射と組み合わせることにより根治が可能であり、必要な治療として強くおすすめします。
子宮頸がんに対する放射線治療の悪影響と対処法について教えてください。
- A
-
子宮頸がんに対する放射線治療の悪影響は主に周囲の膀胱・直腸・小腸などにみられ、薬などで対処します。
子宮体がん、卵巣がん、膣がんや外陰がんではどのような時に有用ですか。
- A
-
病気の種類、大きさ、がん細胞の種類により治療法はさまざまです。適切なタイミングで放射線治療が受けられるよう、担当医とよく相談してください。
直腸がんへの放射線治療はどのような時に行いますか。
- A
-
手術の前や後に、もしくは手術中に行います。術前、術後に用いる時は、通常抗がん剤を併用します。
肛門がんで放射線治療を行うメリットについて教えてください。
- A
-
肛門の扁平上皮がんは放射線治療と化学療法に治療の効果が高く、両者を併用することによって高い確率で完治が期待でき、肛門機能を温存することで、人工肛門にならなくてすみます。
膀胱がんで放射線治療を行うメリットについて教えてください。
- A
-
進行した膀胱がんの場合には、膀胱を温存する手術は難しく、膀胱を全部切り取る必要があります。膀胱を全部取ってしまうため、新しく人工的に膀胱を形成する手術が必要になります。手術の代わりに放射線治療、抗がん剤治療を行うことで、膀胱を温存し排尿機能を維持することが期待できます。
睾丸腫瘍、陰茎がんではどのような時に放射線治療を行いますか。
- A
-
睾丸腫瘍のうち精巣上皮腫(セミノーマ)では、手術後に腹部のリンパ節へ放射線治療を行うことがあります。陰茎がんでは、患者さんが手術に耐えられない場合や、陰茎温存を希望した場合に放射線治療を行います。
-Q19骨軟部(骨、筋肉など)・皮膚への放射線治療について教えてください。
骨転移に放射線療法は効きますか。
- A
-
症状緩和、とくに除痛に関しては、おおむね効果があります。
骨転移に対する放射線治療の方法について教えてください。
- A
-
外部照射、アイソトープ治療(放射線ストロンチウムを用いた治療法)があります。
骨軟部肉腫に放射線治療は効きますか。
- A
-
放射線治療による効果は腫瘍の種類により大幅に異なります。ユーイング肉腫や横紋筋肉腫、形質細胞腫などは、通常の放射線治療でも十分効果があり、その他の腫瘍では粒子線治療が有効です。
骨軟部腫瘍への粒子線治療はどのような場合に有用ですか。
- A
-
根治的切除術が困難な脊索腫や骨軟部肉腫に対して重粒子線(炭素イオン線)治療の有用性が実証されています。
骨軟部腫瘍への放射線治療の悪影響について教えてください。
- A
-
腫瘍のある部位、照射線量、放射線の種類により異なりますが、照射した部位を中心に起こります。
皮膚がんへの放射線治療はどのような時に行いますか。
- A
-
顔面などの手術によって残る傷あとが問題になる場合や、手術ができない場合、やや進行した皮膚がんの術後照射や転移部位に対して行われます。
悪性黒色腫に放射線治療は効きますか。
- A
-
通常の放射線治療は悪性黒色腫に対してあまり効かないのですが、粒子線治療の有効性が報告されています。とくに眼、副鼻腔や鼻腔など頭頸部の腫瘍に対しての有効性の報告が多くあります。
-Q20リンパ・血液のがんへの放射線治療について教えてください。
悪性リンパ腫の放射線療法はどのような場合に有用ですか。
- A
-
悪性リンパ腫は、ホジキンリンパ腫、非ホジキンリンパ腫、その他の節外性リンパ腫に大きく分類されます。病気のタイプや広がりによって違いますが、抗がん剤や分子標的薬剤などの薬物療法を主な治療として、放射線治療を追加治療として行う治療法が一般的です。脳、眼、鼻腔、胃などは、放射線療法だけで治療する場合もあります。
悪性リンパ腫への放射線治療の悪影響について教えてください。
- A
-
放射線治療の対象となる部位とそこに含まれる臓器や組織によって現れる悪影響は異なります。くわしくは各部位や臓器のがんに対する放射線治療の項目を参照してください。
骨髄腫に放射線治療は効きますか。
- A
-
病変が限局して存在する骨髄腫には、完治させるための放射線療法が可能です。病変が多発している骨髄腫では抗がん剤が主な治療法ですが、抗がん剤を行っても痛みや圧迫症状などがある場合、症状を緩和するための放射線治療も有用な補助治療です。
造血幹細胞移植(骨髄移植)のための全身照射とはどのような治療ですか。
- A
-
骨髄にある腫瘍細胞を放射線の全身照射によって根絶し、正常な骨髄を移植するために行われます。治療は1日の朝・晩、あるい3日間の朝・晩に行う方法などがあります。白血球がなくなって抵抗力が下がるので、無菌室に入ることが一般的です。
全身照射の悪影響について教えてください。
- A
-
治療中には吐き気、急性耳下腺炎、下痢などの消化器症状や口内炎、咽頭炎などの粘膜炎が起こることが多いです。治療後では、放射線肺炎、不妊などがあります。
がんのリンパ節転移に放射線治療は効きますか。
- A
-
さまざまながんのリンパ節転移にも放射線治療は有効です。ただし、その有用性はがんの種類や病状によって違います。詳細は各原発部位をご参照ください。
-Q21こどもへの放射線治療について教えてください。
こどもに放射線治療をして大丈夫なのですか。
- A
-
こどもは正常の細胞も放射線の影響が出やすいので、経験を積んだ医療チームが、最適な治療機器を用いて細心の注意を払いながら実施することが大切です。放射線による治療効果を最大にして、しかも放射線特有の悪影響を最小にするように努めています。
こどもとおとなでは照射の仕方が違いますか。
- A
-
放射線治療そのもののやり方は、こどもとおとなで違いはありません。乳幼児のように、数分間、動かないようにすることの協力が得られないこどもについては、全身麻酔や鎮静薬を使いながら、放射線治療をすることがあります。
小児白血病に対する全脳照射はどのような時に行いますか。
- A
-
全身化学療法で投与された抗がん剤は脳内の腫瘍細胞に到達しないことが多いので、頭蓋内の腫瘍細胞を死滅させることを目的に脳に放射線を照射します。
ウイルムス腫瘍ではどのような時に放射線治療を行いますか。
- A
-
腎臓の腫瘍を摘出した後に、腫瘍があった所や、再発や転移した腫瘍がある所を局所的に照射します。
神経芽腫ではどのような時に放射線治療を行いますか。
- A
-
抗がん剤だけで治りにくいタイプの神経芽腫では手術が行われ、手術で取り除けなかった場合には、術後の放射線治療を行うことがあります。
こどもの肉腫ではどのような時に放射線治療を行いますか。
- A
-
腫瘍がある部位に照射して悪性細胞を破壊して腫瘍を縮小させる効果があります。しかし、放射線療法が効きにくい肉腫も多く、手術できない場合や術後に取り残しがある場合、手足を残すための治療などで使用されます。
こどもへの放射線治療の後遺症と対処法について教えてください。
- A
-
こどもの病気に対する放射線治療では、十分な治療効果を得るために、深刻な放射線の影響のリスクを抱えなければならないことがあります。放射線治療による影響の中には、こどもに特有のものもあります。こどもに特有な放射線の影響の代表的なものは、こどもの成長や発達を妨げてしまうという問題です。放射線治療により知能の発達への影響、骨格の成長への影響、性的機能や生殖能の発達への影響が起きることがあります。これらの影響は、命をおびやかすものではありませんが、程度によっては、生活の質に影響を及ぼします。
-Q22がん以外の病気での放射線治療について教えてください。
どのような病気に対して放射線治療を行うのでしょうか。
- A
-
甲状腺眼症、ケロイド、血管腫、動静脈奇形、胸腺腫、良性脳腫瘍など、手術ができない場所にあったり、手術に危険が伴ったり手術だけでは再発しやすい場合、あるいは放射線治療にとって代わる治療法がない時は、がんでなくとも放射線治療が行われます。また、バセドウ病では放射線を出す薬を飲む治療もあります。
甲状腺眼症ではどのような時に放射線治療を行いますか。
- A
-
甲状腺眼症の治療には、ステロイドという種類の薬を使いますが、薬の効きが悪い時、薬を減らすと悪化する時、薬の副作用が強い時、持病のために薬が使えない時などは、放射線治療が行われます。意外に思われるかもしれませんが、放射線治療はステロイドと違って、悪影響がほとんどないのが特徴です。
ケロイドではどのような場合に放射線治療を行いますか。
- A
-
ケロイドの治療法の1つに、手術でケロイドを取り、その部分に放射線治療をする方法があります。1週間程度で治療は終わり、他の治療が効かなかった時の治療法としても用いられています。またケロイドができやすい体質の人では、手術をした後に放射線治療を行うとケロイドの予防になります。
血管腫ではどのような場合に放射線治療を行いますか。
- A
-
血管腫は多くの臓器に生じますが、良性の病気のため最初から放射線治療が選択されることはありません。ほかに有効な治療法がない時や、効果が得られない時に放射線治療が選択されます。
動静脈奇形ではどのような場合に放射線治療を行いますか。
- A
-
脳の動静脈奇形は、脳の大切な働きをする部位にある時や、手術が危険な時に放射線治療が選択されます。また脊髄の動静脈奇形では通常血管内治療が行われますが、治療が難しいか、もしくは効かない時に放射線治療が選択されます。
がんでなくても放射線治療の悪影響は問題ないのでしょうか。
- A
-
がんと良性の病気どちらでも、放射線治療により悪影響は発生することがあります。しかし、がんの治療と比べると、良性の病気では放射線の線量が少ないため、悪影響も少ないといえます。
-Q23放射線治療後の生活について教えてください。
食事など生活上で気をつける点はありますか。
- A
-
口、のど、食道、胃や腸などの消化器に放射線が当たった治療を受けた方は、刺激のあるものや消化の悪いものを避けるなど食事に気をつけましょう。飲酒は過量でなければ大丈夫ですが、口、のど、肺の治療後の方はぜひ禁煙を守ってください。
後遺症が心配なのですが。
- A
-
放射線治療を行う段階で利益もありますが、後遺症も問題になる可能性がある時は、放射線治療の担当医が患者さんに説明をしてから治療を行います。ですから、担当医に説明されていないのであれば、重い後遺症が起こる可能性はとても少ないといえます。
放射線腫瘍科にも通う必要があるのですか。
- A
-
がんの診断はそれぞれの臓器を担当する医師によって行われ、放射線治療の担当医に紹介されたことと思います。放射線治療は専門的な治療ですので、その効果判定、再発や後遺症の診断は放射線腫瘍医が最も的確に行えます。その意味で、放射線腫瘍科にも通院することをおすすめします。
胃腸の不快な症状の対処法について教えてください。
- A
-
放射線治療による消化吸収機能の低下、胃炎、腸炎でも、通常の消化剤や胃炎、腸炎の薬が有効です。症状がある時には、刺激物や消化の悪いものを避けて、消化の良いものを少しずつ食べることをおすすめします。また、便通を規則正しくすることも大切です。
直腸出血や膀胱出血が起きた時の対処法について教えてください。
- A
-
まずは治療を受けた放射線腫瘍科、あるいは放射線治療のことをよく知っている医師に相談しましょう。下血では便の硬さの調節、薬の治療、レーザー治療、高気圧酸素療法などが有効です。血尿では薬の治療、レーザー治療、高気圧酸素療法などが有効です。
後遺症の可能性がある時は誰に相談すればよいですか。
- A
-
放射線治療のことは放射線腫瘍医が一番知っています。治療を受けた放射線腫瘍医、あるいは放射線腫瘍科が患者さんの状況を最もわかっています。放射線腫瘍科に連絡することが難しい場合は、治療当時の病状と放射線治療のことがよくわかっている医師に相談しましょう。
- がん放射線治療のしくみについて教えてください。
-Q24放射線治療は、なぜがんに有効なのですか。
放射線治療でどのようにがんが治るのですか。
- A
-
がん細胞の遺伝子に傷をつけて、がん細胞を死滅させるからです。
放射線治療が効きにくいがん、効きやすいがんはあるのですか。
- A
-
活発に活動し盛んに分裂する細胞ほど、放射線の影響を受けやすいので、早く大きくなるがんは効きやすく、ゆっくりと大きくなるがんは、効きにくい傾向があります。また、酸素が十分に行き渡っていない細胞にはエックス線は効きにくい傾向があります。
正常な部分に影響はないのでしょうか。
- A
-
正常な細胞も放射線の影響から免れることはできませんが、がん細胞に比べてかなり速いスピードでDNAの傷を修復することができるので、少量の放射線を繰り返し照射すると、照射と照射の間に正常組織は少しずつ修復します。最終的には、がん細胞が受ける傷に比べて、正常組織が受ける傷は少なくてすみます。
放射線治療はがん以外の病気にも効くのですか。
- A
-
良性の腫瘍や血管の異常などにも有効です。
-Q25治療に使う放射線の種類と装置について教えてください。
放射線とは何で、どんな種類や単位があるのですか。
- A
-
放射線とは電波のような目には見えない光(エックス線、ガンマ線)や、速く飛ぶ小さな粒(ベータ線、電子線、陽子線、炭素線など)のことです。たくさんの種類がありますが、がん治療によく使われるものはエックス線、ガンマ線、電子線、陽子線です。放射線治療でよく聞くグレイ(Gy)やベクレル(Bq)は単位です。
放射線治療にはどの放射線を使うのですか。
- A
-
放射線治療に使われる放射線には、エックス線、電子線、陽子線、重粒子線、ガンマ(γ)線、ベータ(β)線、アルファ(α)線などがあります。外部照射、小線源治療、粒子線治療、内用療法など治療法により使用する放射線の種類は異なります。
放射線治療にはどのような装置を使うのですか。
- A
-
一般的な放射線治療には、リニアック(直線加速器)で発生させたエックス線が用いられます。患者さんは装置についているベッドに寝て治療を受けます。粒子線治療ではサイクロトロンやシンクロトロンといった大型の加速装置を使い高度な技術を要するので、治療ができる施設は限られています。
-Q26放射線治療の方法について教えてください。
外部照射について教えてください。
- A
-
からだの外から放射線を照射することを総称して外部照射といいます。照射する放射線の種類は、エックス線、ガンマ線、粒子線などすべてを含んだ名称です。小線源治療や内用療法(標的アイソトープ治療)に比べ、ある範囲に均一に照射しやすく、その投与線量を制御しやすいという長所があります。
定位放射線治療について教えてください。
- A
-
定位放射線治療とは、比較的小さい腫瘍に対して多方向から放射線を集中して照射する治療方法です。治療効果を高めることと、腫瘍周辺の正常部位の合併症を低減させることが目的です。通常の放射線治療よりも1回に大量の放射線を短期間に照射します。いわゆる「ピンポイント照射」のことです。
画像誘導放射線治療(IGRT)について教えてください。
- A
-
画像誘導放射線治療は、イメージガイド放射線治療(IGRT : image-guided radiotherapy)ともいいます。放射線治療を行う場合に、治療装置上で撮影した画像により照射位置の微調整を行いながら照射します。放射線治療方法そのものではなく、放射線治療を高精度に行うための補助技術です。
強度変調放射線治療(IMRT)について教えてください。
- A
-
強度変調放射線治療(IMRT : intensity-modulated radiotherapy)とは、放射線の分布を腫瘍に沿った複雑な形状にするために、空間的に不均一な照射ビームを多方向から照射する技術です。とくに放射線治療の標的が複雑な形状で、温存するべき正常組織と近接している場合に力を発揮するので、頭頸部腫瘍や前立腺がんに対してよく用いられます。
粒子線治療について教えてください。
- A
-
粒子線を使った放射線治療のことで、粒子線(Q25参照)のなかでは主に陽子線と重粒子線が使われます。エックス線による一般的な放射線治療に比べて、がん病巣を狙い撃ちできるという大きな長所があります。とくに重粒子線の1つである炭素イオン線は、がん細胞に対する殺傷効果がエックス線の約3倍と強力です。
照射中には息を止めなくてはなりませんか。
- A
-
肺がんや肝がんに対する放射線治療では、呼吸で腫瘍が動いてしまうことが問題です。そこで、息を止めて照射をする方法や、お腹の動きをモニタリングしながらある呼吸位相の時にだけ照射する方法などの対策(呼吸性移動対策)がとられています。
小線源治療について教えてください。
- A
-
放射性物質を小さなカプセルなどに密封しがんの中に入れ、からだの中から放射線を当てる方法です。からだの中から直接放射線を当てることで、できるだけたくさんの放射線をがんに照射し、周囲の正常組織にはできるだけ放射線を当てないようにします。
内用療法(標的アイソトープ治療)について教えてください。
- A
-
ラジオアイソトープ(放射性同位元素)を経口薬や静脈注射により体内に取り込み、投与した放射性薬剤が病気の部分に集まる性質を利用した治療法です。ラジオアイソトープから出る放射線によってがんの治療や疼痛の緩和を行います。
回答に対するさらに詳しい解説は「患者さんと家族のための放射線治療Q&A」編集:日本放射線腫瘍学会、金原出版株式会社 定価:2,640円(2,400円+税)に書かれています。
患者さんと家族のための放射線治療Q&A
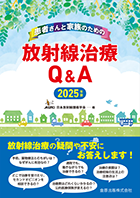
編集:日本放射線腫瘍学会
金原出版株式会社
発行:2025年4月10日
定価:2,640円(2,400円+税)
放射線治療は手術、薬物療法と並ぶがん治療の3本柱の1つで「切らない治療法」と注目される一方、「放射線」という言葉に思わぬ悪影響が出るのではないかと心配する患者さんもいます。そこで本書は、放射線でがんが治るしくみ、治療の進め方や生活
上の注意点、患部ごとの治療法など、“正しい”知識をQ&A形式で簡単に解説します。
